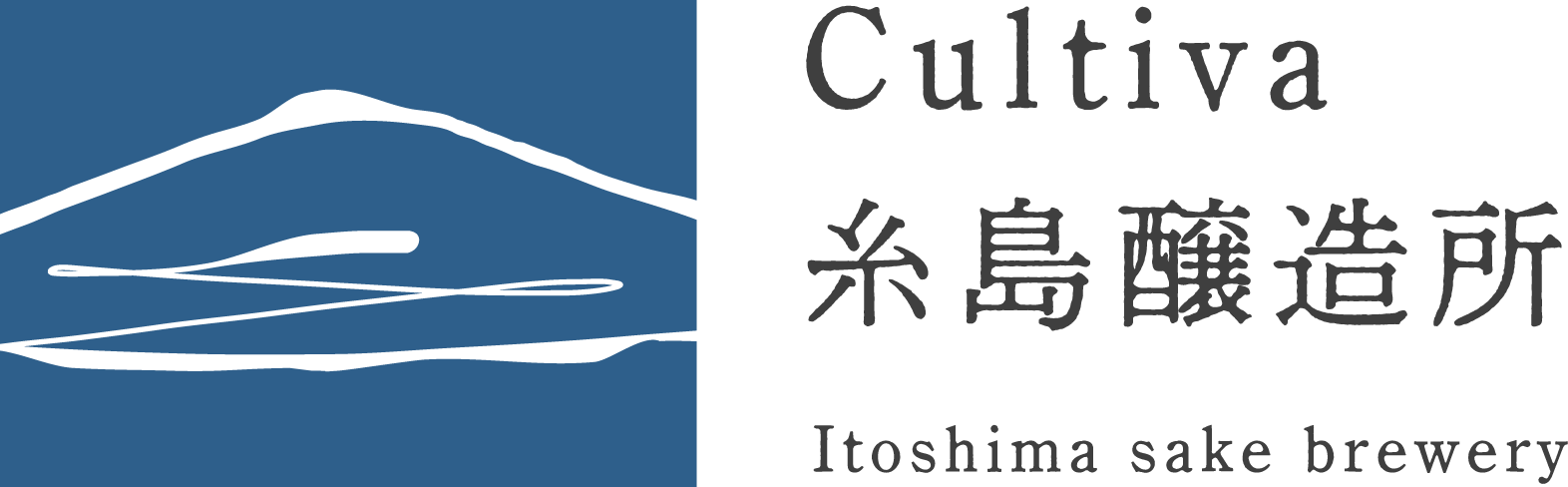素材に重きを置く、新しい価値基準。
 従来の日本酒造りは、製法が主軸とされ、素材である米の個性は埋もれがちでした。福岡県糸島の醸造所 Cultivaはその常識を覆し、「製法中心」から「素材中心」へとシフトする酒造りを行なっていきます。
従来の日本酒造りは、製法が主軸とされ、素材である米の個性は埋もれがちでした。福岡県糸島の醸造所 Cultivaはその常識を覆し、「製法中心」から「素材中心」へとシフトする酒造りを行なっていきます。
この取り組みの背景には、私自身の研究者としての原体験があります。焼酎メーカーの研究職として、原料成分が酒質に与える影響を分析し続けてきました。そうした中で私が強く実感したのは、麹という存在があるからこそ、原料の多様性が香味の多様性として立ち上がるということでした。
米・麦・芋・そば——素材が変わっても、麹と組み合わせることで、それぞれに異なる香りや味わいを引き出せる。麹は、和酒における”多様性の架け橋”のような存在であり、それこそが日本の発酵文化の中核にあると気づいたのです。
この知見を社会に実装するために、私はCultivaを立ち上げました。米の持つ個性を最大限に引き出し、素材の違いを香味の違いとして体験できる濁酒をつくる——それは、和酒の原点である「原料×麹」の関係性に立脚した、新たな酒文化の提案でもあります。
専門性は地域の魅力を最大限に引き出す力となる
 焼酎メーカーでの研究職、そして技術士(生物工学部門)として培ってきた専門知識と分析技術。それらを酒造りに活かし、「酒米テロワール」を軸に据え、地域の自然と文化を科学的に捉えながら、日本酒・どぶろく・クラフトサケ・テロワールなどの理想の味わいをかたちにしていきます。
焼酎メーカーでの研究職、そして技術士(生物工学部門)として培ってきた専門知識と分析技術。それらを酒造りに活かし、「酒米テロワール」を軸に据え、地域の自然と文化を科学的に捉えながら、日本酒・どぶろく・クラフトサケ・テロワールなどの理想の味わいをかたちにしていきます。
焦点を当てているのは、以下のような要素です。
- 原料米のタンパク質やアミノ酸組成
- 生酛、木桶仕込みでの微生物による複雑系
- 熟成による香味の変化
地域の風土がもたらす酒の個性を探求するには、これらの要素の解明が欠かせません。
私にとって酒造りとは何よりも”素材の本質”を追い求める研究の延長線上にあるものです。将来的には。学会発表や論文投稿といったアカデミックな発信も視野に入れつつ、醸造所での研究と実践を積み重ねていきます。
自然と技術の調和こそが酒造りにおける真髄
 茶道の精神を表す言葉に「詫びたるは良し、詫ばしたるは悪し」という文言があります。
茶道の精神を表す言葉に「詫びたるは良し、詫ばしたるは悪し」という文言があります。
この言葉は、人の作為に対して自然の優位を説いていると私は解釈しております。
人の手が自然よりも前面に出ているものは、美しさを損ねているのではないでしょうか。
そうではなく、自然の力に寄り添い、そこに委ねた仕込みこそが、真に美意識の高い酒造りだと私は確信しております。
しかし、同時に、よりおいしく、美しいお酒を追求するためには、伝統に縛られることなく、新しい技術を積極的に取り入れる姿勢も必要です。
合理化や効率化だけを目指す技術は自然優位なものづくりにそぐいませんが、自然の力を最大限に引き出すことは、技術の役割だと考えます。
私が目指すのは、「伝統への回帰」と「新しい技術による発展」の両立です。
この回帰と発展を融合させることで、次世代の酒造りの形を切り開けると確信しております。